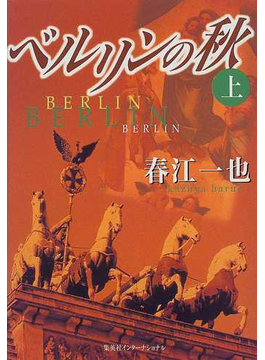 掲題の作者が書いた「中欧三部作」なるシリーズものの2作目であるこの本を読んだ。図書館の予約が立て込んでいた事情があって、2作目ながら最後にこれを読んだ。1作目の「プラハの春」が作者自身が外交官としてチェコの民主化運動に立ち会い、つぶさに経験した想いをあふれんばかりに描いていて共感を覚えた。第2作はその後編として、東ドイツの「ベルリンの壁崩壊」をテーマにした作だが、前作のヒットを意識しすぎたか、より背伸びしようとして邪念が入ったようで、ちょっと期待外れだった。史実の部分とラブロマンスの部分が乖離していて、歴史小説と官能小説が入り乱れたような出来に見えた。東欧の民主化とソ連の崩壊をも巻き込んだ壮大なテーマを描いたので、どうしても無理が生じたのであろう。まあ、当時の世情をよく知るには納得できる内容ではあった。奇異に感じたのは、ブレジネフやアンドロポフの国家元首がまるで殺人鬼のように暗殺命令するくだりはここまで書いていいのか、ふと作家のペンの横暴さに戸惑いを感じた。
掲題の作者が書いた「中欧三部作」なるシリーズものの2作目であるこの本を読んだ。図書館の予約が立て込んでいた事情があって、2作目ながら最後にこれを読んだ。1作目の「プラハの春」が作者自身が外交官としてチェコの民主化運動に立ち会い、つぶさに経験した想いをあふれんばかりに描いていて共感を覚えた。第2作はその後編として、東ドイツの「ベルリンの壁崩壊」をテーマにした作だが、前作のヒットを意識しすぎたか、より背伸びしようとして邪念が入ったようで、ちょっと期待外れだった。史実の部分とラブロマンスの部分が乖離していて、歴史小説と官能小説が入り乱れたような出来に見えた。東欧の民主化とソ連の崩壊をも巻き込んだ壮大なテーマを描いたので、どうしても無理が生じたのであろう。まあ、当時の世情をよく知るには納得できる内容ではあった。奇異に感じたのは、ブレジネフやアンドロポフの国家元首がまるで殺人鬼のように暗殺命令するくだりはここまで書いていいのか、ふと作家のペンの横暴さに戸惑いを感じた。

