 今日の安曇野は雨予報でしたが、雨は降らず最高気温は32.0℃と蒸し暑い日でした。このところ最高気温は例年よりも4〜5℃も高い日が続いています。でも梅雨空で湿気が多く、カラッとした夏はまだ先のようです。さて、今回の夏の花シリーズはエキナセアと言う花で、我が家では写真の如く勝手口の脇に咲いています。地植えの宿根草で今年で3年目を迎えました。菊のような花弁ですが、淡いピンク色がいいですね。冬は枯れて根しか残らないですが、こうして夏になると見事に花が咲き、頼もしい限りです。この花、ネットで調べるとハーブの仲間のようで、効用として風邪やインフルエンザの予防にもなるようです。ますます、頼もしく思えてきました。
今日の安曇野は雨予報でしたが、雨は降らず最高気温は32.0℃と蒸し暑い日でした。このところ最高気温は例年よりも4〜5℃も高い日が続いています。でも梅雨空で湿気が多く、カラッとした夏はまだ先のようです。さて、今回の夏の花シリーズはエキナセアと言う花で、我が家では写真の如く勝手口の脇に咲いています。地植えの宿根草で今年で3年目を迎えました。菊のような花弁ですが、淡いピンク色がいいですね。冬は枯れて根しか残らないですが、こうして夏になると見事に花が咲き、頼もしい限りです。この花、ネットで調べるとハーブの仲間のようで、効用として風邪やインフルエンザの予防にもなるようです。ますます、頼もしく思えてきました。
我が家の夏の花(6)エキナセア
美ヶ原ハイク
今日は午後からの天候が危ぶまれたのですが、うちのオバはんと日本百名山の一つ、「美ヶ原」に登ることにしました。前回6/19の長峰・光城山ハイクで敢えなくダウンしてしまい、日頃のトレーニング不足を痛感しました。あれから何ら練習に励んだわけでもないのですが、もし今日もダメだったら当面、山は諦めようかと悲壮な思いで登リました。と言うのは登山開始直後までで、予想外に天気が良く稜線に出るとその景色の素晴らしさに悲壮感などすっかり影を潜めました。ルートは三城牧場から百曲がりコースで塩くれ場、アルプス展望コースから山頂の王ヶ頭を目指し、帰路はダテ河原ルートで元の三城牧場に戻る約10kmのハイキングです。写真は山頂に伸びる美ヶ原高原の登山道から電波塔がある山頂方向を眺めたものです。右手にはノンビリと牛もいて、まさに天空のパラダイスでした。昼食そしてコーヒータイムと十二分に休憩をとって下山し、持病の左ひざ痛が出ることもなく、気分揚々と引き上げてきました。以下は3枚の写真を合成したパノラマで、クリックをすると4000×1500ピクセルの大画面にリンクします。リンク先は1.7MBの写真なので、アクセスに時間がかかるようでしたら、ご容赦ください。
最後のジャガイモ掘り
 今日の安曇野は今年一番の暑さで最高気温は35.2℃の猛暑日でした。県内ではこれまた一番の暑さで、二番目は35.0℃の長野市だったようです。家の中もそこそこに暑く、室温の最高は29.2℃でした。エアコンがないので、扇風機を夕刻に廻しました。まあまあ、凌げます。ところで、本日は畑のジャガイモを全部、掘り出しました。品種は今年はキタアカリのみとしました。写真のごとくで、大小様々です。今年はできが悪いと聞いていたのですが、我が家では例年ほどの出来栄えでした。もっと前に収穫する予定が、先日の大雨で粘土質の畑がいつまでも乾かず、様子見していました。何分、保存するには洗ってはいけないようで、本来ならば乾いた泥が望ましいのですが、写真のごとく表層はウェットな状態です。今日の収穫量は10kg弱で、今年は全部で15〜20kgほどだと思います。保存できるのは4ヶ月ほどで、オバはんとの二人暮らしには十分な量です。もうすでに初物は食べましたが、美味しくいただいています。今年も豊作で、めでたし、メデタシ。
今日の安曇野は今年一番の暑さで最高気温は35.2℃の猛暑日でした。県内ではこれまた一番の暑さで、二番目は35.0℃の長野市だったようです。家の中もそこそこに暑く、室温の最高は29.2℃でした。エアコンがないので、扇風機を夕刻に廻しました。まあまあ、凌げます。ところで、本日は畑のジャガイモを全部、掘り出しました。品種は今年はキタアカリのみとしました。写真のごとくで、大小様々です。今年はできが悪いと聞いていたのですが、我が家では例年ほどの出来栄えでした。もっと前に収穫する予定が、先日の大雨で粘土質の畑がいつまでも乾かず、様子見していました。何分、保存するには洗ってはいけないようで、本来ならば乾いた泥が望ましいのですが、写真のごとく表層はウェットな状態です。今日の収穫量は10kg弱で、今年は全部で15〜20kgほどだと思います。保存できるのは4ヶ月ほどで、オバはんとの二人暮らしには十分な量です。もうすでに初物は食べましたが、美味しくいただいています。今年も豊作で、めでたし、メデタシ。
村上春樹「騎士団長殺し」イデア・メタファー編を読んで
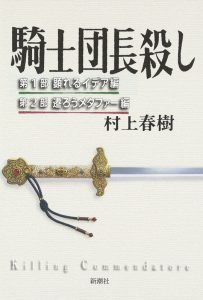 今年2月にこの本が出て久しいが、ようやく2冊を読むことができた。図書館予約が殺到し、第1部を借りるのに約3ヶ月、続きの第2部は第1部を読み終えてから2週間のブランクがでたが、7月になってようやく入手できて3日間で読み終えた。読後の感想を一言で言えば、とにかく読んだの感だが、具体的にはいろいろあって複雑な心境だ。まず、この本のジャンルは何だろう。前作の長編「IQ84」はファンタジー&推理小説のつもりで読んだが、今回の本は分類が難しい。敢えて言うならば、第1編のサブタイトルにあるイデア、「観念」をテーマにした私小説なのだろう。哲学者プラトンがイデア、その弟子のアリストテレスがメタファー(暗喩、明確でないたとえ)を唱えたが、この哲学用語をサブタイトルにしたところが春樹らしい。物語は現実と非現実の世界を彷徨い、今回はナチや南京事件の出来事まで絡んだハルキワールドだ。荒唐無稽で全く現実離れしている物語なのに、それをあたかも本当のことのようにグイグイと惹きつけて読者を没頭させてしまうことができるのは、さすが村上春樹の筆力の凄さでまたしても感心させられた。ネットでこの作品の評価を調べてみたが、賛否両論だ。ただ、売れ行きは予想に反して伸びず、予定した130万部の半分は返品になる見込みの情報もあった。毎年、ノーベル文学賞の候補にもなる作家だが、本作品は少年少女の健全な読み物とは程遠いものであるのは確かだ。
今年2月にこの本が出て久しいが、ようやく2冊を読むことができた。図書館予約が殺到し、第1部を借りるのに約3ヶ月、続きの第2部は第1部を読み終えてから2週間のブランクがでたが、7月になってようやく入手できて3日間で読み終えた。読後の感想を一言で言えば、とにかく読んだの感だが、具体的にはいろいろあって複雑な心境だ。まず、この本のジャンルは何だろう。前作の長編「IQ84」はファンタジー&推理小説のつもりで読んだが、今回の本は分類が難しい。敢えて言うならば、第1編のサブタイトルにあるイデア、「観念」をテーマにした私小説なのだろう。哲学者プラトンがイデア、その弟子のアリストテレスがメタファー(暗喩、明確でないたとえ)を唱えたが、この哲学用語をサブタイトルにしたところが春樹らしい。物語は現実と非現実の世界を彷徨い、今回はナチや南京事件の出来事まで絡んだハルキワールドだ。荒唐無稽で全く現実離れしている物語なのに、それをあたかも本当のことのようにグイグイと惹きつけて読者を没頭させてしまうことができるのは、さすが村上春樹の筆力の凄さでまたしても感心させられた。ネットでこの作品の評価を調べてみたが、賛否両論だ。ただ、売れ行きは予想に反して伸びず、予定した130万部の半分は返品になる見込みの情報もあった。毎年、ノーベル文学賞の候補にもなる作家だが、本作品は少年少女の健全な読み物とは程遠いものであるのは確かだ。
松本市街地の花
 今日はうちのオバはんと松本の市街地に行ってきました。平均すれば、月に1、2回は出かけるのですが、この時期は街頭の花が目立ちます。やはり花があると華やいでいいですね。何ぶん、松本市は観光地として力を注いでいて、城以外でもいろんな催し物があるようです。先月は「松本市花いっぱい運動」のイベントがありました。大方の道には今日の写真のように花が飾られ、観光客はじめ誰もが街並みの美化に触れることができます。このイベントのために花が飾られるのではないと思いますが、日頃からボランティアが街の景観に一役買っていて、イベントを通して普段通りの姿をアピールしているようです。今日のブログは我が家の花シリーズの番外編でした。
今日はうちのオバはんと松本の市街地に行ってきました。平均すれば、月に1、2回は出かけるのですが、この時期は街頭の花が目立ちます。やはり花があると華やいでいいですね。何ぶん、松本市は観光地として力を注いでいて、城以外でもいろんな催し物があるようです。先月は「松本市花いっぱい運動」のイベントがありました。大方の道には今日の写真のように花が飾られ、観光客はじめ誰もが街並みの美化に触れることができます。このイベントのために花が飾られるのではないと思いますが、日頃からボランティアが街の景観に一役買っていて、イベントを通して普段通りの姿をアピールしているようです。今日のブログは我が家の花シリーズの番外編でした。
久しぶりの芝刈り
 先日の大雨の後、しばらく好天が続いています。それまではずっとぐずついた天気で、庭の芝は伸び放題になっていました。久しぶりに芝を刈ったのですが、昨日、今日と2日がかりでした。最初に芝刈り機で全体を刈り、次にハンディのバリカンのようなツールでエッジなどを刈り上げます。このハンディタイプのものが充電式なので、30分ほどでバッテリーが切れてしまい、再充電しての作業で2日に及んでしまうのです。まあ、急ぐ作業ではないのでこうして2日がかりの芝刈りが定着しています。前回は1ヶ月ほど前でしたが、これから梅雨が明けると芝もよく伸びるようになり例年、月に2〜3回ペースで芝刈りすることになります。今年は芝の成長が少し遅く、やっと全体が緑になりました。やれやれです。
先日の大雨の後、しばらく好天が続いています。それまではずっとぐずついた天気で、庭の芝は伸び放題になっていました。久しぶりに芝を刈ったのですが、昨日、今日と2日がかりでした。最初に芝刈り機で全体を刈り、次にハンディのバリカンのようなツールでエッジなどを刈り上げます。このハンディタイプのものが充電式なので、30分ほどでバッテリーが切れてしまい、再充電しての作業で2日に及んでしまうのです。まあ、急ぐ作業ではないのでこうして2日がかりの芝刈りが定着しています。前回は1ヶ月ほど前でしたが、これから梅雨が明けると芝もよく伸びるようになり例年、月に2〜3回ペースで芝刈りすることになります。今年は芝の成長が少し遅く、やっと全体が緑になりました。やれやれです。
温又柔「真ん中の子供たち」を読んで
 今回の芥川賞候補の一つだが、退屈な小説だった。日本人と台湾人とのハーフの子供が中国語を習いに上海の学校に行き、そこで過ごした日々を回想めいて綴っている。原稿枚数にして224枚の中編で1日で読み終えたが、とにかく読み進めるのが億劫だった。まあ最後には何らかの感動、或いは爽やかな読後の余韻でも残るのではないかと期待したが、結局何も残らなかった。文章が新進気鋭の鋭さや切れ味の凄さがあるでもなく、普通のタッチだった。何を書きたかったのかよく分からず、いつもながら芥川賞候補なるが故の面白みのない典型的な作品だった。このような作品でも結構、評価され受賞するパターンがよく散見されるので、今回はどうなるかそれだけが気になった。
今回の芥川賞候補の一つだが、退屈な小説だった。日本人と台湾人とのハーフの子供が中国語を習いに上海の学校に行き、そこで過ごした日々を回想めいて綴っている。原稿枚数にして224枚の中編で1日で読み終えたが、とにかく読み進めるのが億劫だった。まあ最後には何らかの感動、或いは爽やかな読後の余韻でも残るのではないかと期待したが、結局何も残らなかった。文章が新進気鋭の鋭さや切れ味の凄さがあるでもなく、普通のタッチだった。何を書きたかったのかよく分からず、いつもながら芥川賞候補なるが故の面白みのない典型的な作品だった。このような作品でも結構、評価され受賞するパターンがよく散見されるので、今回はどうなるかそれだけが気になった。
我が家の夏の花(5)シャラとヤマボウシ
昨日はかなりの雨が降り、安曇野市も一時は大雨警報に引き続き土砂災害警戒情報も発令されました。幸い被害はなかったものの庭も畑も水浸しでした。今日は雨も止み日差しも戻り、ホッとしました。それにしても九州は今だに豪雨が続いているようで、何とも痛ましいかぎりです。ところで、今日のブログは夏の花の第5弾で、草花ではなく樹木の花にしました。写真は今日撮った庭の様子です。この時期、庭先のシャラとヤマボウシは白い花が咲き、今が丁度見ごろです。写真左はシャラで花数は少ないのですが、咲くと存在感があります。冬場は細々とした枯れ枝は見る影もないのですが、こうして緑豊かに蘇って花も咲かせてくれます。一方、ヤマボウシは木全体が花で覆われて華やかです。よくぞ咲いてくれたと言った感じですが、散ると掃除も大変です。樹木の夏の花、季節感があっていいですね。

沼田真祐「影裏」を読んで
 今月は年2回の文学賞で有名な芥川賞と直木賞の発表がある。少し前から図書館ではノミネートされた作品が掲示されていて、芥川賞候補の題記の本を借りて読んでみた。原稿枚数にして93枚、短編に属するこの小説は半日にして読めた。日常生活を淡々と綴った平易な文章だが、不思議な小説だった。岩手県の自然の美しさと釣りの醍醐味が多分に描かれ、終盤は東日本大震災の話に連なるが、一体何が書きたかったのかよくわからなかった。友人との心のふれあいがテーマなのだろうが、謎かけやほのめかしなどの心理を突くような文体ではなく、ミステリータッチの雰囲気もない、ただただみずみずしさだけが印象に残った小説だった。以前に「芥川賞の偏差値」と言う受賞にまつわる評論を読んだが、その筆者が賞を取る秘訣は「いかにもうまいという風に書いて、かつ退屈であることが重要」と力説していたことを思い出した。今回読んだこの本はなるほど然り、と思われるのでひょっとすると賞を射止めるかも知れない。
今月は年2回の文学賞で有名な芥川賞と直木賞の発表がある。少し前から図書館ではノミネートされた作品が掲示されていて、芥川賞候補の題記の本を借りて読んでみた。原稿枚数にして93枚、短編に属するこの小説は半日にして読めた。日常生活を淡々と綴った平易な文章だが、不思議な小説だった。岩手県の自然の美しさと釣りの醍醐味が多分に描かれ、終盤は東日本大震災の話に連なるが、一体何が書きたかったのかよくわからなかった。友人との心のふれあいがテーマなのだろうが、謎かけやほのめかしなどの心理を突くような文体ではなく、ミステリータッチの雰囲気もない、ただただみずみずしさだけが印象に残った小説だった。以前に「芥川賞の偏差値」と言う受賞にまつわる評論を読んだが、その筆者が賞を取る秘訣は「いかにもうまいという風に書いて、かつ退屈であることが重要」と力説していたことを思い出した。今回読んだこの本はなるほど然り、と思われるのでひょっとすると賞を射止めるかも知れない。
長野県民は標高自慢?
 今日のタイトルは何のことやら分からないと思われる方は正常な方、と言うよりも長野県以外の方と言った方がよろしいのではと思います。テレ番で「ケンミンSHOW」と言うのがありますが、日本全国津々浦々、どの県にもおらがお国自慢があります。では長野県は何かと言うと、それは標高ではないでしょうか。と言うのも長野県民はことあるごとに標高にそれはそれは執着するのだそうです。日本で標高の一番高い県は誰しもが長野県であることは言わずもがなですが、それを自慢にしていることを私はこちらに移住して初めて知りました。確かにそうなのでしょう。道路を走っていても市境の標識には地名の他に、必ず標高が記載されているのを見るにつけ、ここは長野県だと身構えてしまいます。で、あなたの居場所の標高は、何ちゃって..。
今日のタイトルは何のことやら分からないと思われる方は正常な方、と言うよりも長野県以外の方と言った方がよろしいのではと思います。テレ番で「ケンミンSHOW」と言うのがありますが、日本全国津々浦々、どの県にもおらがお国自慢があります。では長野県は何かと言うと、それは標高ではないでしょうか。と言うのも長野県民はことあるごとに標高にそれはそれは執着するのだそうです。日本で標高の一番高い県は誰しもが長野県であることは言わずもがなですが、それを自慢にしていることを私はこちらに移住して初めて知りました。確かにそうなのでしょう。道路を走っていても市境の標識には地名の他に、必ず標高が記載されているのを見るにつけ、ここは長野県だと身構えてしまいます。で、あなたの居場所の標高は、何ちゃって..。


