 冬シーズンも終わり蛍雪の時季も過ぎ去ったのに、おかしなタイトルですが、実は悲しいお知らせです。先月の自治会の会合で地元の市会議員の方から、「4月からJR穂高駅が無人駅になる」旨の発言がありました。過疎化と客離れで路線の収益が圧迫し、かなりの赤字なのだそうです。切替えはどうやら明日からのようで、その様子を写真に撮ってきました。でも、駅のお知らせには明日、4/20から「みどりの窓口」が営業終了と記されているだけで無人駅になるとは書かれていませんでした。安曇野市は観光施策に重点を置いていて、その中心地で観光の玄関口でもある穂高駅の無人化はないだろう、いや、大都市と田舎との2極化は深刻で地方の憂いは止めようがないのが実態か。この無人化の真偽のほど、今後、検証していきたいと思っています。
冬シーズンも終わり蛍雪の時季も過ぎ去ったのに、おかしなタイトルですが、実は悲しいお知らせです。先月の自治会の会合で地元の市会議員の方から、「4月からJR穂高駅が無人駅になる」旨の発言がありました。過疎化と客離れで路線の収益が圧迫し、かなりの赤字なのだそうです。切替えはどうやら明日からのようで、その様子を写真に撮ってきました。でも、駅のお知らせには明日、4/20から「みどりの窓口」が営業終了と記されているだけで無人駅になるとは書かれていませんでした。安曇野市は観光施策に重点を置いていて、その中心地で観光の玄関口でもある穂高駅の無人化はないだろう、いや、大都市と田舎との2極化は深刻で地方の憂いは止めようがないのが実態か。この無人化の真偽のほど、今後、検証していきたいと思っています。
蛍の光、穂高駅
しだれ桜も満開..?
 安曇野エリアの平地ではソメイヨシノが満開となりました。信州の今年の桜は数日前に開花したところが多く、そして今や満開になったようです。ローカルニュースでは開花からたった3日間で満開となり、新記録だと報じていました。おととい穂高川の桜が2〜3分咲きと思っていたのですが、本日見に行ったところ正に満開でした。今日は風速15mを越す風が吹き荒れていて、散るのも今年は最短記録になるやも知れません。明後日に予定した花見宴会までは何とかもって欲しいと早春賦の碑に拝んできました。さて、しだれ桜はどうなったか調べに堀金・田多井まで出かけてきました。知る人ぞ知る、知らない人は全く知らない、しだれ桜の名所で、他県からもカメラマニアが多く訪れる所です。そして写した写真が今日の1枚です。少し満開を過ぎた感じでしたが、4年ぶりに見る桜はやはり圧巻でした。夕刻の陽が落ちた後の写真で写りはイマイチですが、見上げたその大きさは流石に迫力がありました。安曇野のしだれ桜は多くが墓地にあって、ここも山麓のお墓にあります。ついでに平地のしだれ桜を数カ所巡ってきましたが、すでに時は遅く散ったところでした。ソメイヨシノは今や満開なるも、しだれ桜はピークを過ぎたことを再認識した1日でした。
安曇野エリアの平地ではソメイヨシノが満開となりました。信州の今年の桜は数日前に開花したところが多く、そして今や満開になったようです。ローカルニュースでは開花からたった3日間で満開となり、新記録だと報じていました。おととい穂高川の桜が2〜3分咲きと思っていたのですが、本日見に行ったところ正に満開でした。今日は風速15mを越す風が吹き荒れていて、散るのも今年は最短記録になるやも知れません。明後日に予定した花見宴会までは何とかもって欲しいと早春賦の碑に拝んできました。さて、しだれ桜はどうなったか調べに堀金・田多井まで出かけてきました。知る人ぞ知る、知らない人は全く知らない、しだれ桜の名所で、他県からもカメラマニアが多く訪れる所です。そして写した写真が今日の1枚です。少し満開を過ぎた感じでしたが、4年ぶりに見る桜はやはり圧巻でした。夕刻の陽が落ちた後の写真で写りはイマイチですが、見上げたその大きさは流石に迫力がありました。安曇野のしだれ桜は多くが墓地にあって、ここも山麓のお墓にあります。ついでに平地のしだれ桜を数カ所巡ってきましたが、すでに時は遅く散ったところでした。ソメイヨシノは今や満開なるも、しだれ桜はピークを過ぎたことを再認識した1日でした。
有終のポインセチア
穂高川の桜、咲き始めました
ジャガイモにネギと...
松本城の桜
上越市、高田公園の桜
今日はうちのオバはんと新潟県は上越市にある高田公園に出かけました。ここの桜は日本三大夜桜として有名なのだそうです。今日の長野県は全県、晴れマークで天気が良いと思ったのですが、新潟県は午前中は雨、午後は晴れたり曇ったりそして雨が降ったりと急がしい天気でした。おまけに温度は10℃以下で肌寒く感じました。お目当ての高田公園は今が満開の勢いで、広範囲に植えた桜でどこを向いても桜だらけでした。さすが日本3大名所に名を恥じないスケールで、見事でした。平日ながら人出が多く駐車場は河川敷の特設エリアも満車で、遠く徒歩30分ほど離れた駐車場に誘導されました。この混雑も3大スケールなのでしょう。新潟の桜は今回が初めてですが、ソメイヨシノをはじめとした桜に変わりはなく、長野県よりも北に位置するのに早咲きなのを再認識しました。白馬から糸魚川を経由して上越市へ、帰路は妙高高原から長野市を周遊して一般道の約280kmの旅、信州だけが桜に取り残された感がしました。
タイヤ交換しました
気になる桜ですが、自宅近くの穂高川沿いはまだ蕾でした。一昨日、松本城の桜が開花となりましたが、信州の桜名所の多くはまだ開花していません。まあ、じきに開花となるでしょう。ところで、今日は車のタイヤ交換をしました。例によって、アウタロウのExcelデータからタイヤ交換表を最下部に切り貼りしました。この表はタイヤ着脱の日付を入れると走行距離と日数を自動計算するもので、1代目スタッドレスタイヤ(S1)は総走行距離が10,974 kmで、半年強、装着していました。今日からノーマルタイヤ(N1)の出番ですが、2巡目に入って今日現在までに11,453km、7ヶ月以上の装着期間です。今回の実績では夏冬タイヤとも1シーズン、11,000kmほど走っていて、寿命の目安を30,000 kmとすると3シーズンは使用できそうです。でも、来る年には夏冬両方のタイヤを新品にするのはちょっとシンドいので貯金でも始めようか、などと思ったりして...
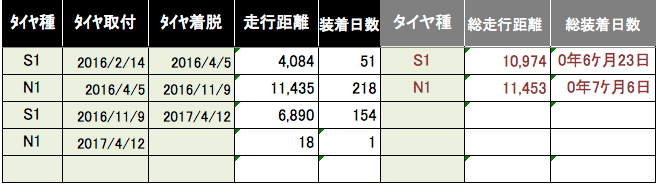
この半年の車の走行データ
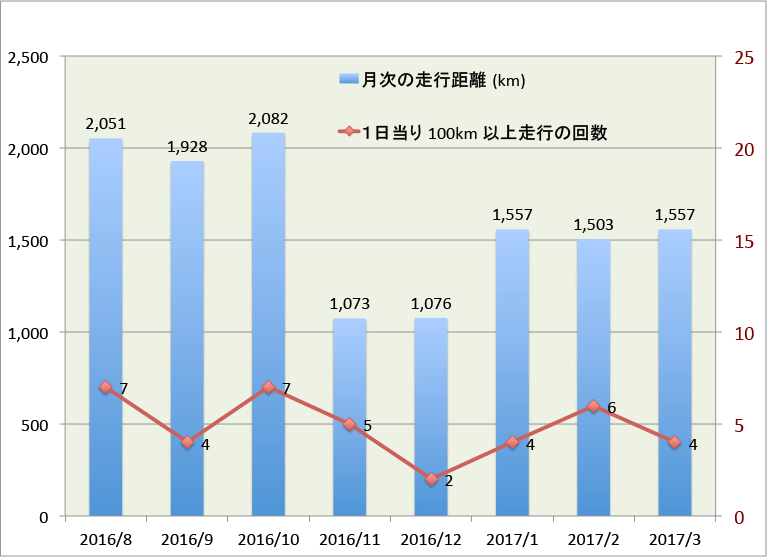 各地の桜情報も満開のところが多くなりました。でも今日は1日中雨が降り続き、桜見物はお預けです。4月は天候不順の日が多いようです。今日はExcelの勉強がてら、我が家のアウタロウの走行データをグラフ表示してみました。昨年8月から各月の走行距離と1日に100km以上走行した月次の回数を表示しています。面白いのは、8月から10月までの3ヶ月間は月間で2000km ペース、11月と12月は1000km台に落ち込み、1月から3月までの3ヶ月は1500kmと復調気味です。特に500kmごとに月次でコントロールしたわけではないのですが、奇しくも3つのグループに分かれました。とりわけ1月と3月は1557kmと走行距離が一致して驚きました。傾向を見ると、最初のグループは夏から秋の行楽、冬前は小休止して、スキーシーズンはその中間の1500kmレベルで推移したようです。ちなみに1日の走行が100km以上となったのは各月、2〜7回で平均月5回前後のようでした。これからは春シーズン、まずは観桜など小さな旅をはらんでどのように推移するか、気になります。
各地の桜情報も満開のところが多くなりました。でも今日は1日中雨が降り続き、桜見物はお預けです。4月は天候不順の日が多いようです。今日はExcelの勉強がてら、我が家のアウタロウの走行データをグラフ表示してみました。昨年8月から各月の走行距離と1日に100km以上走行した月次の回数を表示しています。面白いのは、8月から10月までの3ヶ月間は月間で2000km ペース、11月と12月は1000km台に落ち込み、1月から3月までの3ヶ月は1500kmと復調気味です。特に500kmごとに月次でコントロールしたわけではないのですが、奇しくも3つのグループに分かれました。とりわけ1月と3月は1557kmと走行距離が一致して驚きました。傾向を見ると、最初のグループは夏から秋の行楽、冬前は小休止して、スキーシーズンはその中間の1500kmレベルで推移したようです。ちなみに1日の走行が100km以上となったのは各月、2〜7回で平均月5回前後のようでした。これからは春シーズン、まずは観桜など小さな旅をはらんでどのように推移するか、気になります。
今年の神代ザクラ
今日は山梨県北杜市の山高神代(ヤマタカジンダイ)桜の観桜に出かけました。昨年に引き続き、2回目です。樹齢およそ2000年と言われる日本一古い桜は今年も健在でした。エドヒガンの神代桜は満開、廻りのソメイヨシノは7、8分咲きで、去年よりも人出が多く大変賑わっていました。今年の桜は昨年よりも10日遅れと言った感じです。写真は境内の全景をつなぎ合わせてパノラマ化したもので、遠く甲斐駒ヶ岳の左下が神代桜です。クリックすると、幅5000pixelの写真(1.6MB)にリンクします。花々の咲きっぷりをトクトご覧ください。南諏訪から山梨県へ国道20号を南下すると、一気に標高が下がり景色は一変して、北杜の里は春爛漫でした。帰路は清里から佐久を経由しておよそ270kmを周遊しました。温暖な山梨に比べ、信州はまだまだ冬の固さの残っているのを肌で感じた1日でした。







