すっかり春めいてきました。と言うか、このところ初夏のような陽気で、昨夜はシーズン初めて薪ストーブを炊くのを止めました。暖かくなったものです。散歩も薄着になりました。以下の写真は道中に撮ったもので、とても情緒ある民家に出くわしました。三方が堀で覆われて湧水の清流となっていました。最後の1枚はよく見かける光景で、当ブログでも似た風景をよく投稿しますが、何ともうららかな春になったものです。
2026年3月 日 月 火 水 木 金 土 « 2月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31





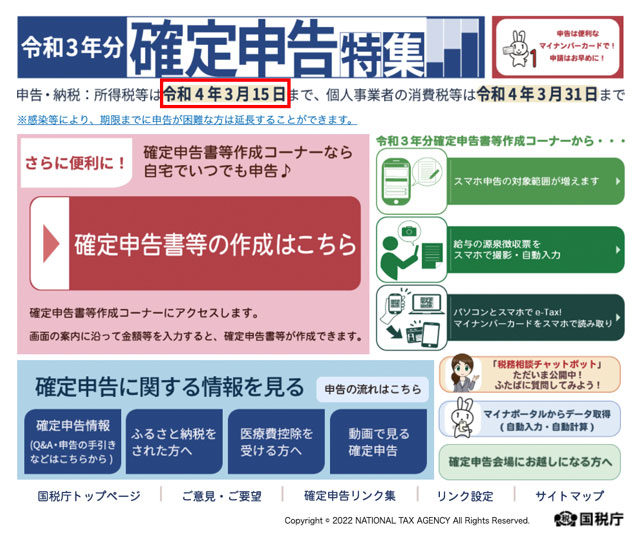















 羽田圭介の新刊を読んだ。物を持たない主義のミニマリストの物語。何でもかんでも捨てまくる行きすぎたミニマリストだが、途中から捨てられない過去の話が延々と出てきて作者の言わんとするところが分かりにくかった。題名がどこから来るものかも推察困難で、ミニマリストの抱える矛盾をテーマにしたような小説だった。自分にとっては肌の合わない物語、そして作風。少なくともシニア向けではないのは明らかな感じだ。
羽田圭介の新刊を読んだ。物を持たない主義のミニマリストの物語。何でもかんでも捨てまくる行きすぎたミニマリストだが、途中から捨てられない過去の話が延々と出てきて作者の言わんとするところが分かりにくかった。題名がどこから来るものかも推察困難で、ミニマリストの抱える矛盾をテーマにしたような小説だった。自分にとっては肌の合わない物語、そして作風。少なくともシニア向けではないのは明らかな感じだ。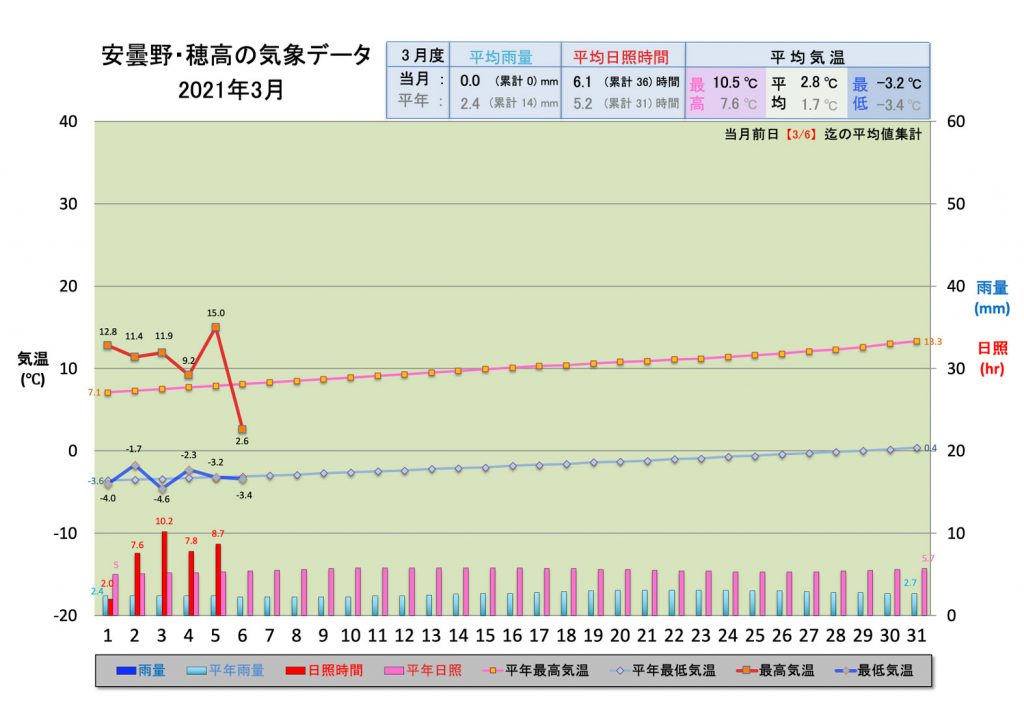
 先般の直木賞候補作である題記の本を読んだ。学生時代のクラブで知り合った男女4人のそれぞれの悩みをオムニバス短編で綴った物語だ。途中までは物語に引き込まれのめり込んで読んだが、面白みが薄らぎ何となく読み終えた感じの本だった。著者は初めて読む作家で、名前から当初は男性作家のように思われ読み進んだが、文体がどうしても女性タッチで調べるもなく女流作家であることを感じ取った。本の帯に「愛するものの喪失と再生を描く、感動の物語」とあったが、そこまでの感情移入は生じなかった。直木賞を逃したのは相応と感じた。
先般の直木賞候補作である題記の本を読んだ。学生時代のクラブで知り合った男女4人のそれぞれの悩みをオムニバス短編で綴った物語だ。途中までは物語に引き込まれのめり込んで読んだが、面白みが薄らぎ何となく読み終えた感じの本だった。著者は初めて読む作家で、名前から当初は男性作家のように思われ読み進んだが、文体がどうしても女性タッチで調べるもなく女流作家であることを感じ取った。本の帯に「愛するものの喪失と再生を描く、感動の物語」とあったが、そこまでの感情移入は生じなかった。直木賞を逃したのは相応と感じた。