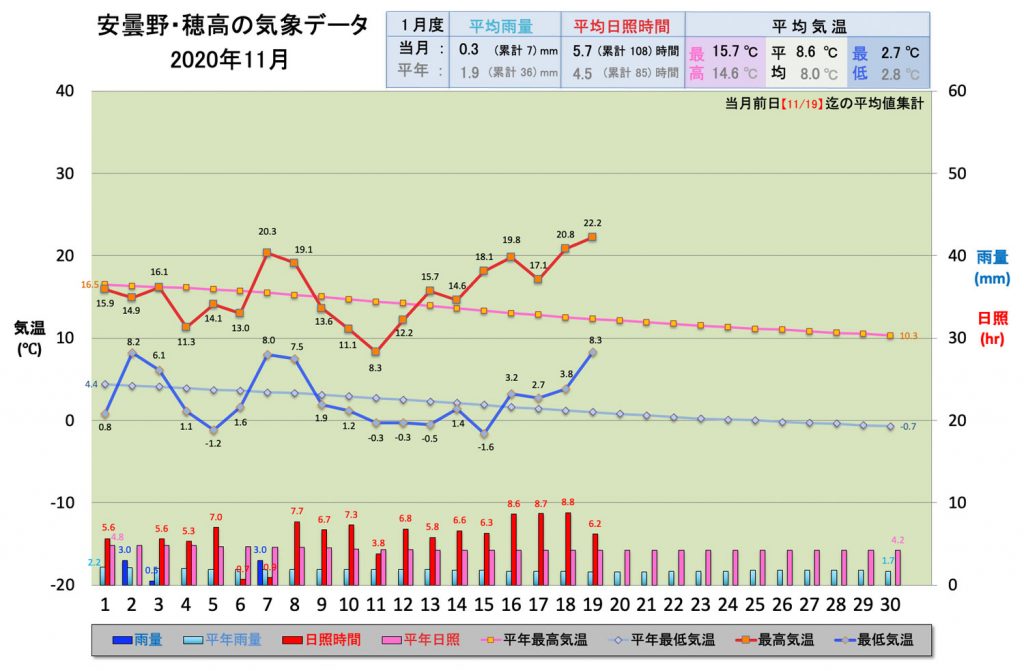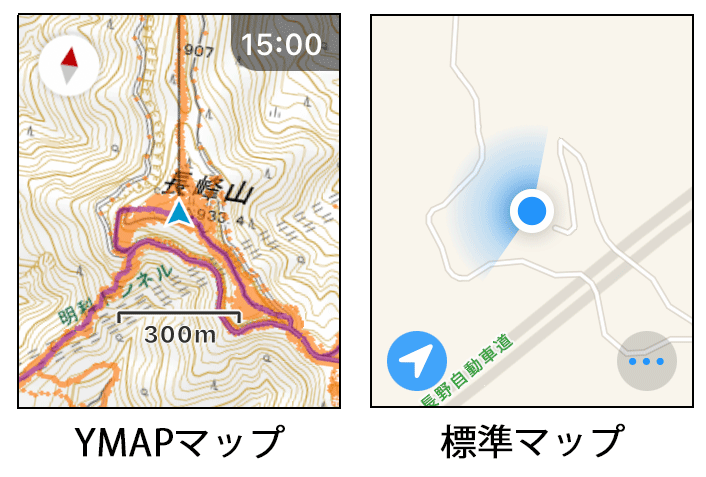先週金曜日が雨そして連休3日間がドライブと、このところ運動不足でしたが、今日はまとまって歩きました。自宅周辺をくまなく歩くようにしてからまだ出向いていない堀金地区まで行ってきました。行きはGoogle Mapの徒歩最短コースで「堀金」道の駅まで行くとジャスト6kmでした。帰路はあづみ野やまびこ自転車道を中心に戻ると7kmを超えていました。今日は午前中の暖かいさ中に歩いたので、いい汗をかきました。無風快晴の陽気でとてもいいウォーキングでした。このところ慣れてきた一人ウォークです。右に本日の歩行コース、下の写真に一言添えましたのでクリックしてご覧ください。
先週金曜日が雨そして連休3日間がドライブと、このところ運動不足でしたが、今日はまとまって歩きました。自宅周辺をくまなく歩くようにしてからまだ出向いていない堀金地区まで行ってきました。行きはGoogle Mapの徒歩最短コースで「堀金」道の駅まで行くとジャスト6kmでした。帰路はあづみ野やまびこ自転車道を中心に戻ると7kmを超えていました。今日は午前中の暖かいさ中に歩いたので、いい汗をかきました。無風快晴の陽気でとてもいいウォーキングでした。このところ慣れてきた一人ウォークです。右に本日の歩行コース、下の写真に一言添えましたのでクリックしてご覧ください。
- 少しの間、大糸線沿いを歩きます
- 進行方向右手には北アルプス
- 左手は松本方面です
- 民家の間の道から抜けられそうです
- 車道なのに車はほぼ0
- のどかな景色です
- 堀金地区の行政支所に到着
- 安曇野の名付け親、臼井吉見の記念館です
- 終点の堀金物産店
- 今日は昼から奮発メニュー
- 常念岳が見えてきました
- 帰路は自転車道がメインです
- 常念と有明山の名コンビ
- 信州の伝統的家屋が様になってる
- ここで自転車道とお別れ
- 学区の小学校、もう家も近し